~HarFor Breaking Interview#08 土佐備長炭 一(ICHI)近藤寿幸さん~
HarForがオフィスを構える高知で、解決できる課題、実現できる未来は一体なんなのか。高知を一緒に盛り上げていく素敵な方々からお話を伺うインタビューシリーズ、「HarFor Breaking Interview」。HarForが大切にする「つながり」をテーマに、ゲストのご縁を繋げていくリレー企画です。
第七回のゲスト、山のくじら舎社長の萩野和徳さんが繋いでくれた八回目のゲストは、土佐備長炭 一 の近藤寿幸(こんどう としゆき)さんです!よろしくお願いいたします。
(近藤さん)ーよろしくお願いします!

~プロフィール~
天理大学を卒業後、剣道の指導を志し、教師を目指し高知へ帰省。
剣道を通じて障がい者福祉や、土佐備長炭の職人の仕事と出会い
炭焼きの仕事に障がい者雇用の可能性を見出し、炭焼職人へと転身する。
(インタビュアー)炭焼き職人になる前は、特別支援学校の先生をされていたんですよね?
(近藤さん)はい。元々剣道をしていたのですが、大学生時代「高知で学校の先生になって剣道を教えたい!」と思うようになって。人の成長を支援する仕事にとても魅力を感じていたこともあり、保健体育の先生を目指していました。ただ、最初は講師にもなれなかったんです。そんな時に、たまたま剣道を通じて障がい者施設で働かせていただくことになりました。福祉施設では3年働きましたが、どうしても学校の先生になる夢を諦めきれず、講師登録し直したらご縁があり、日高の特別支援学校に配属されることになりました。
(インタビュアー)そこからまた、全く異なる「炭焼き職人」の道に進むんですね。
(近藤さん) はい。日高で3年間働いた後、山田の特別支援学校で1年間講師を務めました。その時に剣道を通じて土佐備長炭の職人さんに出会ったのが、この道に入るきっかけです。 実際に窯元に出向き、職人の方から17ある製造工程を聞いたのですが、障害を持つ方々でも支援すれば一緒に作業ができるのではと可能性を感じたんです。そして、自分が障がい者雇用の受け皿になり、同じような取り組みが広がれば、 東部地域でも障がい者雇用が増やせるんじゃないかと思いました。周りからは大反対を受けましたが、それを押し切って職人の世界に飛び込みました。
(インタビュアー) 大反対があったんですね。
(近藤さん)両親もそうでしたし、剣道関係者や友人からも大反対を受けましたね。特別支援学校で働いていた時から、一次産業が中心の高知県東部地域には障がい者雇用の受け皿が足りないと、学校で他の先生たちともずっと話していました。
 ▲周囲の反対を押し切って炭焼職人の世界へ転身。障がい者雇用の可能性を信じ、
▲周囲の反対を押し切って炭焼職人の世界へ転身。障がい者雇用の可能性を信じ、
「自分が受け皿になりたい」という強い想いが決断の原動力だったそうです。
(インタビュアー) 実際にこの世界に飛び込んで、大変なことはありますか?
(近藤さん) 本当にたくさんありますが、まず、障がい者の方々と一緒に、炭焼きという過酷な環境での重労働をどうやって乗り超えるかが課題でした。夏場は特に辛く、僕自身も休みがなくてすごく大変だったので、正直「この仕事を選んだのは間違えたかも」という思いが何度も頭をよぎりましたね。
でも、僕は教師を辞める際、障がい者雇用をすると啖呵を切って辞めたんです。なのにそれを諦めて、また学校の先生に戻ったり、他の仕事をしていたりしたら格好悪いじゃないですか。なので、意地ですね(笑)独立して2、3年くらいは意地でなんとかやっていました。そこから、今年の7月で独立してちょうど10年です。
(インタビュアー)10年という節目の年なんですね! おめでとうございます。
(近藤さん)ありがとうございます!独立後3年目くらいから本格的に障がい者雇用を始めました。 障がい者雇用の形ではありますが、実質雇用形態は一般の人と一緒で、給与は一般の人の最低賃金と同じです。

▲辞めるといった以上言葉に責任を持ちたいと自身の決断を貫いた近藤さん。
その意地と覚悟が、障がい者と歩む炭焼職人としての10年間を支えてきたんだと感じました。
(インタビュアー) 障害を持つ方々と働くにあたって、働き方にはどんな工夫をされているのでしょうか?
(近藤さん)特別支援学校や福祉施設で得た知識なども活かし、働きやすい環境づくりを行っています。 例えば、知的障害の方向けに物にはラベリングを施す視覚支援を行ったり、自助具を考えたり、動画で客観的に見てもらったりと、働くしくみ自体にも工夫をしています。ただ、この3年ほど、そうした支援をいくら重ねてもどこかしっくりこない部分がありました。
その理由を考えたときに、 障害の有無ではなく「人」だと思ったんです。 人と向き合う内面的な部分が足りていないと気づき、仕事の合間に時間を見つけて、心理学や脳科学からカウンセリング技術や言葉の掛け方を勉強し始めたんです。
(インタビュアー)すごいですね!
(近藤さん) そこで改めて大事だと分かったのが「適材適所」ですね。誰でも不得意なことを任されるのは嫌です。炭焼きの現場でも、その人ができることに取り組めるような環境を作ることを大事にしています。一歩を踏み出すというのはすごく勇気が必要なので、支援を通してやる気を促し、自分が何が得意で何が苦手なのかということを相手が気づくまで待ちます。この「待ち」の時間が最初はかなりかかりました。
(インタビュアー)最初に雇用された方はどんな方だったんですか?
(近藤さん) 安芸市の「農福連携」の取り組みを土佐市で聞いた方が、県の職員さんを通じて僕のところへいらっしゃいました。僕より少し年上の、人生経験豊富な方でした。今全国的に農福連携という、障がい者の方が農業で活躍することで自信や生きがいを持って社会へ参画することを実現するための取り組みが注目されています。
その方は知的障害をお持ちで、自分で考えて動線を組み立てたり、計画的に取り組んだりすることが苦手でした。ただ、経験したことを軸にとにかく前に進むという力はあったので、まずは「一緒にやってみる」ところから始めました。例えば、iPadを使って僕の動きと本人の動きを視覚的に比較してみせたり、コーチングのように対話し、本人が「あ、こういうことか」と気付く瞬間を作ってみたりなどのサポートを行いました。
(インタビュアー)そういった方法は、心理学などから学んだんですか?
(近藤さん)いや、実は心理学の知識を用いる以前から、その「気付き」がすごく重要なことだというのは感じていて、自然と大切にしていましたね。こうやって実際に障がい者の方と一緒に働くようになったことで、もっと色んなアプローチを身に着けた方が良いなと気付き、深く学ぼうというきっかけが生まれました。
(インタビュアー)今は何人くらいの方が働かれていらっしゃるんですか?
(近藤さん)今は僕と、女性が2人の3人です。1人は事務担当の一般の方で、もう1人は「ゆりっぺ」という、ADHDと自閉症の重複障害をもった女性です。元々彼女は炭焼きをやりたくてうちに来ているわけではありませんでした。両親から様々な虐待を受け、高知市内に逃げてきていた子です。親に束縛されて生きてきたので「家族は必要ない、 自分に必要なのは自由だ」と、3年前来たばかりのときは人のことを信じられず、人と目を合わせることもなかったのですが、 今はすごく変わりましたね。僕をいじるようになったりして(笑)昨年は農福連携コンソーシアムという全国の大会で発表を行い、春には新聞にも載りました!

▲作業着姿の『ゆりっぺさん』の写真
(インタビュアー)働くことで、大きな変化があったんですね。
(近藤さん)窯で働くことと同時に、カウンセリングとコーチングをプロのコーチにお願いしたことが変化に繋がったと思います。仕事においてはうまくできないことには必ず原因があるので、その原因に寄り添って方法を考えています。例えばADHDの方々の場合、情報が次々と頭の中に入ってきて集中力散漫になりやすい特性があるので、やることを極力シンプルにしてあげます。
その一つとして、「作業スケジュール」というものを書いてもらっています。ただその日の作業日誌を書くのではなく、前の日にやった作業を基に次の日の作業を自分で組み立ててもらうんです。マルチタスクをシングルタスクに分解して自分のゴールを設定し、そのゴールに向けて何をしたらいいかという道筋を逆算して計画を具体化していきます。この時、スタートの8時には何をするか、それは誰とやるのか、という風に最初の一歩をすごく簡単なところまで細分化するのがポイントです。人間って、最初のハードルを越えたら自然と前に進んでいけるような構造になっているので、最初のハードルは特に低く設定します。こういった少しのコツで、簡単にうまくいくようになります。
「勉強が続かない」という人は、まずは机に座って本を開くだけというところから自分が気づいて設定すると、5分もすればできるようになりますよ!
(インタビュアー)へー!やってみます!
(近藤さん)今後はそういったきっかけを、彼ら自身が自分で引き出していけるようになるかが課題ですね。それに対し、自分も心理学や脳科学を学んで勉強していっています。
この炭焼きの仕事を通じて、自分自身の視野もすごく広がりました。前回のゲストの山のくじら舎の萩野さんなど、色んな人から教わったり、本などから学んだりして、その人にあった支援は何なのか、仕事とは何なのか、人としての在り方は?等、日々考えてます。
(インタビュアー)萩野さんからも!
(近藤さん)萩野さんは起業当初住んでいたアパートのご近所さんで、長い間お世話になっています。食にこだわりがあってお家でも料理の際に備長炭を使ってらっしゃって、そこからうちの炭を使ってくださるようになったんです。今では県外出張の際など、食事をしに行ったお店で炭がないという話を聞けば営業までしてくださっています(笑)
そんな萩野さんに一番最初に繋げていただいたのが日本を代表する京都の料亭さんなのですが、うちの炭を使っていただいていて、【①同一規格 ②爆ぜない ③燃焼時間が長い ④ 高火力】という、炭の4つの評価基準が全て満たされている炭は初めてだと、嬉しいお言葉をいただきました。

▲時間をかけて丁寧に作られるからこそ、使われ続ける土佐備長炭の魅力
(インタビュアー)とてもこだわって作られてるんですね。
(近藤さん)そうですね、少しの手間を大切にしています。
例えば炭は湿気を吸ったり吐いたりする性質があるのですが、炭は中の湿度が高いと爆ぜやすくなるので、高温多湿な日本では注意が必要なんです。そこで、湿気を防ぐために僕が取り入れているのが、ハウス栽培などに使われるビニールです。他の職人さんは灰から取り出してきた炭をそのままコンクリートの上に置くのですが、 コンクリートも湿気を通すので、そのままだと湿度がどんどん炭の中に入っていってしまいます。 それを、コンクリートの上にハウスのビニールを敷いて炭を包むだけで、ビニールが湿度を遮断し炭の中の湿度を一定に保てるようになります。
このようなヒントは日常によくあるものから取り入れています。今回は高知ではよく見かけるビニールハウスから得ました。こういったひと手間がお客さんの満足に繋がります。
(インタビュアー)土佐備長炭は、他の地域の備長炭と何か違いはあるんですか?
(近藤さん) 紀州備長炭が備長炭発祥の地で、 その他宮崎の日向備長炭や、愛知の尾張備長炭など、色んな所に備長炭はありますが、そんなに大きな違いはないですが、原材料によって個性があります。
基本的に備長炭というのは、一般的な炭と比べて密度が高く、一定の火力を長時間維持することができるという特徴があります。なので調理に向いています。
原材料はウバメガシとカシの2種類の木で、特にウバメガシは金メダル級の貴重な素材です。土質や日照条件等が変われば、木の密度も変わります。日がよく当たる場所に生えたかそうじゃないかで、木の密度が変わります。厳しい環境で育つと密度が高くなるので、火力も燃焼時間も長くなるんです。
(インタビュアー)そんな違いがあるんですね!そういった木は、高知で採れたものなんですか?
(近藤さん)はい。どうしても地元で採る必要があるんです。大体20日間のサイクルで備長炭はできるのですが、 窯の中で行う「乾燥」という工程では、原木の中の含水率が非常に重要です。原木内の水分によって起こる「熱収縮」の原理を使って、密度の高い炭にしていくのですが、水分が足りなかったり、過乾燥になってしまったりすると、内部応力によって割れ目が多く入ってしまうんです。そのため、その水分をしっかり保った状態で窯の中に入れる必要があります。県外から材料を持ってくるとなると伐採後の経過時間が長くなり、自然乾燥によって水分が失われてしまうのですよ。品質が保てなくなってしまうんです。

▲作業中のお写真
(インタビュアー)ここで少し、備長炭作りの工程について教えていただけますか?
(近藤さん)まずはチェーンソーを使って原木を伐採し、伐採した原木を180センチくらいに切る「玉切り」を行います。その切ったものを、今度は一本一本人の手で運搬車まで運び、今度は運搬車でクレーン付きトラックがあるところにまで運んで積み替え、やっとの思いで窯まで運びます(笑)
窯まで運んだ原木を、今度は適切なサイズに割っていきます。原木は割らないと大きすぎるというのと、そのままだと粗悪な炭になりやすくなるんです。割ったものは、窯の天井の両サイドに4.5トンずつ並べ、ここから窯を使った工程が始まります。並べられた原木を釜の中に入れていく「窯くべ」と呼ばれる工程です。
(インタビュアー)この作業は主に近藤さんがされているんですか?
(近藤さん)そうですね!重たい原木を、400~500度に熱した窯の中に一本一本手作業で入れていきます。一度に約9トンの原木を焼くのですが、窯から出てくる時には10分の1以下の、900キロほどにまでになってしまいます。窯くべでのポイントは、木と木が重なるように入れていくことです。原木は収縮によって長さが70%ぐらいに縮んでしまうので、うまく重ねないと隙間ができ、 窯から出す時に空気が通って燃焼して炭が減ってしまいます。
原木をくべた後には1日かけて「蒸し込み」という乾燥の工程があり、続けて10日間かけての「乾燥」の工程に入ります。乾燥が十分に効くと、次は「炭化」の工程に入ります。この炭化では、出てくる煙が重要になるんです。炭化初日の夜、この工程が順調であれば4時間おきに、順調でなければ2時間おきに窯の煙の色・量・匂いを確認しなければなりません。うまくいっていないときは寝られないですね(笑)
(インタビュアー)大変な作業だ!すごく熱そうです!

▲大きな窯の写真
(近藤さん)窯は高いところで2m80㎝、横幅は3m60㎝くらいあって大きく、窯から出す時には中の温度は1000〜1200℃にもなっているんです。なので窯の前に行くと、「熱い」とかじゃなくて「痛い」ですね。でも、 窯の中は本当にきれいです。初めて見た時はとても感動しました。
「炭化」の後は窯の中に空気を少しずつ入れ、炭から不純物を取り除いて純度を高める「練らし」という作業を行い、炭を窯から出す「窯出し」へと進みます。窯出しでは約14〜16時間かけ、「トリマタ」という道具を使って炭を挟んで鉄かごの中に取り出していきます。取り出した炭は何もせず置いておくと灰になってしまうので、「素灰」というものをかけて2日ほど冷まします。素灰が表面につき、白くなった「白炭」と呼ばれる炭を、ダイヤモンド粒子が付いた刃でカットし、選別・箱詰めして完成です!
これらの作業は同時進行で進めていきます。乾燥に大体10日かかるので、その間に最後の炭の「切断」から「箱詰め」までの仕上げ工程を終わらせます。 残りの10日間では、炭化している間に山に行って伐採して、木を運んできてから割って並べるまでの工程を行います。
(インタビュアー)忙しい!休みがないですね。
(近藤さん)1人でやっていた最初の3年間は、効率も悪いし、休むのも不安だし、休まずずっと仕事していました。1年目とかは、ゆっくり休めたのはお正月の1日だけでしたね。
(インタビュアー)大変なお仕事ですが、実際に働かれている方々の様子はどうですか?
(近藤さん)ゆりっぺは幼いときから社会人になるまで、生きるために必要な色んなピースが欠けていました。「働く」ということについても、考え方がちょっと子供っぽいというか。僕らもそうですが、大学を卒業したときなど、奉仕される側からする側に頭を切り替えるのって中々難しいですよね。そういった「働く」ということの意識付けが結構大変だなと感じます。自分の役割をしっかり認識し、今何をしなければならないかを考える意識が本人の中で芽生えてくると、次第に分かってくるのかなと思っています。
ただ、そもそも引きこもりで誰も信じられなかったような彼女が、ここまで成長したということはすごいことです。ここから先どう成長していくかは本人次第ですが、一緒に仕事をしていきながら見守っていきたいです。
(インタビュアー)そんな暖かい居場所があるのは安心感がありますね。
(近藤さん)安心して生活できる環境と働ける場所の両方が整っていないと、仕事に集中できないですよね。人はどうしても人間関係が大事になってくるので、まずはうちの職場が居場所になるような環境づくりを意識しています。どれだけ仕事ができても、この「居場所」の存在が不安定な人はどこかで倒れてしまうと思うので、こういった基礎づくりには重きを置いていますね。自分の支えとなる居場所づくりに繋がるきっかけになればと思っています。
以前働いていた方が、「障がい者として生まれてよかった」という風に言ってくれたことがありました。障害があったからこそうちで働くことになり、自分自身が変わるきっかけを得ることができたからと。そんな風に、ここで働いているうちに自分に自信ができ、やりたいことが見つかって外に飛び出していけるようになるのも、とても嬉しいことですね。
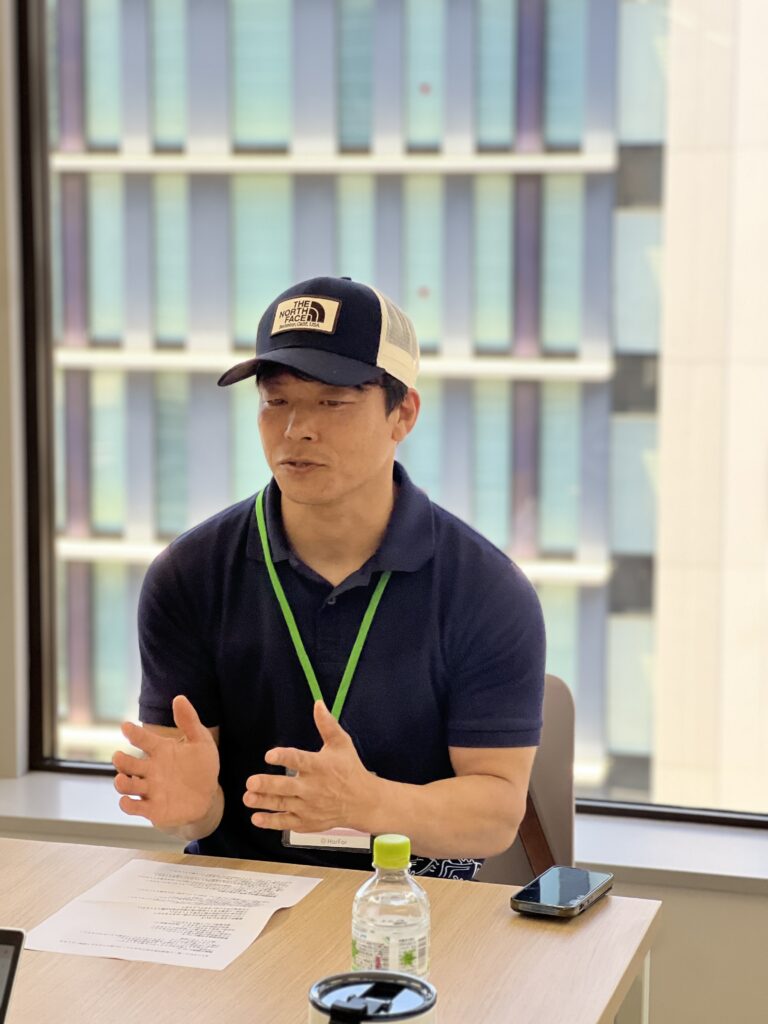
▲炭づくりから植われた新しい雇用のカタチ
その居場所を広げる活動を今後も続けたいと語る近藤さん。
(インタビュアー)「居場所が欲しい」と感じている方は、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。そんな方々へ、どんなことを伝えたいですか?
(近藤さん)ケースバイケースだと思いますが、今私が大切だと考えていることは、まず「自分を知ること」でしょうか。人は案外、自分のことが見えていないものです。「自分を知ること」は認めたくない点も認める必要性が出てきます。それを受け入れるのはとてもしんどいです。まずは自分がどんな人間で、何が得意なのか、しっかり向き合って見つめ直すところから始めてみるといいと思います。自分にないものではなくあるものに目を向け、「自分を活かせる生き方」を選ぶ方が、人生はきっと豊かになると思います。
僕も昔は、自分よりもできる人を見て自分と比べてしまい、自分の外に評価の基準を置いてしまっていました。でも心理学や、一緒に働く仲間たちの姿から『成長は相対評価だけで決まるものではない』と学んだんです。会社などの組織では、つい他者と比較してしまうことが多くなってしまうかもしれませんが、その意識を変えるだけで気持ちが大きく変わっていくと思います。
(インタビュアー)大切な意識ですね。高知でもそんな居場所が今後、どんどん増えていってほしいです。
(近藤さん)今は「個」が注目され、強く主張されるような世の中ですよね。でも、人が集まる「コミュニティ」があって、それがいくつも集まったものが「町」です。だからこそ、色んなもの、色んな人が在っていいとする、「大きな集合体」としての捉え方も大切だと思うんです。そうしないと、逆に個を責めることに繋がってしまうんじゃないでしょうか。そういう意味で、「地域」の在り方が一度見直されてもいいんじゃないかと思っています。バランスを取りながら人(他人)を認め、受け入れられるような「地域」であったらいいですね。
結局、人は人と関わることでしか変わることができません。独立してから10年、様々な人と関わる中で自分自身も実感しています。僕が今の仕事を続けていられるのも、市役所や県の福祉事務所、JA、そして実際に働く障がい者の方々からそうでない方々まで、みんなが互いに認めあい、人と人を繋ぐネットワークを築いてくれたからこそなんです。そういったAIにはできないような人と人を繋ぐシステムが、県内、県外と、どんどん広まっていったらいいなと思っています。
(インタビュアー)なるほど。
(近藤さん)色んな価値観が集まったこの世の中で、「多様性を認める」誰かの居場所づくりは、これからも続けていきたいです。まずは小さな規模から、少しずつ僕の考えに賛同してくれる人が集まってきてくれたら嬉しいですね。うちには来てくださる方を全員受け入れられるようなキャパシティがないので、一緒に受け皿を担ってくれるような仲間がいたらいいなと思います。「一」の取り組みをきっかけに、みんなが自分らしく働ける場所がどんどん増えていってほしいです。
(インタビュアー)人が集まれば、意見交換などもしてお互いさらにより良い取り組みができるようになりそうですね。
(近藤さん)いいですね!色んな方から色んな考え方を聞きたいです。それこそ、僕が今こうして多くの人と関わるようになったのも、炭焼きを始めたからこそなんです。屋号である「土佐備長炭 一」の「一」という文字には、そんなきっかけの部分を大事にしたい、ここから始めていきたいという思いを込めています。
実は高知では、この「一」という文字が昔から特別な意味を持ってきました。例えば「御祝一(おいわいいち)」という文化では、ご祝儀袋の水引の下に右肩上がりに図太く「一」を書き、そこから始まるお祝いや縁を願います。また、高知城の城主・山内家の最も古い家紋「白黒一文字紋」も、「戦いに勝つ」と縁起を担いだシンプルな「一」のデザインです。
こういった形で「一」は歴史や文化の中で大切にされてきました。この特別な「一」のもとで唯一無二の炭を作り、そしてその一本の炭をきっかけとして人と人を繋いでいって、やがて大きな平和の「和」を生み出していきたいと思っています。


▲(左)取材時に着用していたものを撮影させていただきました。
近藤さん、取材へのご協力本当にありがとうございました!
今回の取材内容以外にも、色んなお話をお聞きできました。そちらの楽しい取材の様子も、番外編としてHarForの公式Xで順次公開しますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
次回、近藤さんはどんなゲストにバトンを渡してくれるのでしょうか。お楽しみに!
◆時短勤務等多様な働き方を支援するHarForの採用サイトはこちらから
◆前回の記事はこちらから
◆次の記事はこちらから
(インタビュー・写真:HarFor広報担当)