~ HarFor Breaking Interview#07 山のくじら舎 代表取締役・萩野和徳さん 萩野陽子さん ~
HarForがオフィスを構える高知で、解決できる課題、実現できる未来は一体なんなのか。高知を一緒に盛り上げていく素敵な方々からお話を伺うインタビューシリーズ、「HarFor Breaking Interview」。HarForが大切にする「つながり」をテーマに、ゲストのご縁を繋げていくリレー企画です。
第五回のゲスト、毛利製麺株式会社の毛利仁人さんが繋いでくれた第七回目のゲストは、高知県安芸市でひのきを使った「木のおもちゃ」の製造・販売を行う、山のくじら舎の代表取締役の萩野和徳さん、陽子さんご夫妻です!よろしくお願いいたします。
(和徳さん、陽子さん)ーよろしくお願いします!
 ▲上段(左から2番目)和徳さん、下段(左から2番目)陽子さん
▲上段(左から2番目)和徳さん、下段(左から2番目)陽子さん
~プロフィール~
代表の萩野和徳さんは大阪府、陽子さんは広島県出身。
2001年に和徳さんのご両親の出身地である
高知県安芸市に夫婦で移住し、陽子さんと共に「山のくじら舎」を設立。
全国で注文が殺到する「木のおもちゃ」の製造・販売を行っている。
(インタビュアー) お二人は県外のご出身なんですよね。
(陽子さん)私は広島出身です。最初からモノづくりの仕事をするつもりがあったわけではなかったのですが、思い返してみると全部が繋がっていますね。大学では幼児教育を学び、卒業制作で木のおもちゃを作りました。その時はただ、物作りが好きだったから作ったという感じです。
その後の就職は幼稚園などではなく、IT系の一般企業に就職しました。就職した当時はまだインターネットが珍しく、広島でも最先端の会社でした。就職氷河期の真っ只中でしたが、学生時代からアルバイトしていたこともあってそのまま入れてもらい、カスタマーサービスの仕事をしていました。
(インタビュアー)じゃあ元々デジタルは結構お詳しいんですね。
(陽子さん) いやいや、デジタルの世界ってすごいスピードで進化するから、当時やっていたことはもう今では必要なくなっていることも多くて!お客様からインターネットがうまく繋がらないなどのトラブルの相談に乗るような窓口対応をしていました。今だったら簡単にできますが、当時は自分で設定しなければならないことも多く、うまく対応できないという方も多かったんです。
でもそういった過去の経験も、今の仕事の役に立っているなと思います。今もネット販売が中心なので、直接お客様と顔を合わせる機会も少なく、似たような対応をすることがあります。
(インタビュアー) その時の経験を今も活用されてるんですね。
(陽子さん)そうですね。そのあと少しだけ、実家の近くで学童保育のアルバイトにも行ったりしていました。子供と一緒に遊ぶのが好きですね。
それから結婚と同時に高知へ来ました。主人は大阪生まれ大阪育ちなんですが、主人の両親が安芸出身で。一緒に暮らす場所を考えてた時に、そういった縁もあって高知にやってきました。最初は気候がちょっと肌に合わなくて、暑さとか湿度にやられていましたね(笑)最近も暑さがすごくて、これからの夏の湿気が少し恐怖です(笑)
(インタビュアー) 生粋の高知県民でも中々湿気はキツいです…(笑)
仕事をしている中では子育てとの両立も大変だったかと思うのですが、それはいかがでしたか?
(陽子さん)子供がまだ小さいうちはスタッフも少なく、ほとんど夫婦2人だったので、割と時間も自由にありました。なので、傍で遊ばせながら仕事をしていました。
木のおもちゃを作り始めたきっかけも、そんな子供とのかかわりの中にあるんです。最初は自分の子供に遊んでもらうおもちゃを作ってみようって思って作り始めました。一緒にお風呂で遊べる木のおもちゃです。それが結果的には事業に繋がっていきました。


▲子供との時間から生まれた、ぬくもりあふれる木のおもちゃたち。
(インタビュアー) 山のくじら舎が作る木のおもちゃの魅力やこだわりって何でしょうか ?
(陽子さん)まずは素材でしょうか?自分で作るようになる前は、私も売っている木のおもちゃを買ってきて子供に遊ばせていたのですが、一般的な木のおもちゃって大体広葉樹でできてるものが多いんです。ひのきで作ってる木のおもちゃに、私はあまり出会うことはなかったんですね。ただ、この場所で自分で作るとなった時に手に入りやすい材料が「ひのき」で。杉もあるのですが、ひのきの方が油分があり、 締まっているのにそれでいて柔らかく、加工するのにも削りやすくて形を作りやすいというメリットがあったので、ひのきを使うようになりました。
(インタビュアー) へー!そんなに違うんですね!
(陽子さん)その代わり、遊ぶ時に広葉樹に比べて傷がつきやすいということがあります。それは逆に、また削ったら綺麗になる、メンテナンスがしやすいということでもあるので、手にとって使われる方がご自分でまたメンテナンスをして、愛着を持って長く使っていただけたらいいなと思っています。修理依頼もたまにありますが、ご自分でやすりをかけたり、本当に簡単なメンテナンスだけでとても綺麗になるんです。
もちろんプラスチックのおもちゃもいいところはあると思うのですが、やっぱりすぐに劣化しちゃいますよね。でも木はメンテナンスすればずっと長く使えるし、だんだん色も飴色になってきて、味が出てきます。
(インタビュアー) 素敵ですね。大人も欲しくなりそうです。
(陽子さん)工房に実際に買いに来られるお客様もいらっしゃるのですが、贈り物を選ぶ大人たちの方が、子どもたちより興奮していたりして(笑)やっぱり、実際に手に取って見ていただくとまた違うと思います。
(インタビュアー) ご愛用者様もたくさんいらっしゃる中で、実際に購入された方からのお声などはどんなものがありますか?
(陽子さん)色んなエピソードをいただきますが、最近寄せられたお話の中で面白かったのは、嚙み心地がいいからか、カラスにおもちゃを取っていかれたというお話です(笑)お風呂で濡らして遊ぶ「おふろでちゃぷちゃぷ」というおもちゃをベランダで乾かしていたところ、1つ持っていかれちゃったそうです(笑)
(インタビュアー) ええ〜!カラスも欲しくて狙ってたんですね。
(陽子さん)あと、よくおっしゃっていただくのはやはり、「修理しながら上の子から下の子へ長く使っています!」とか、「おもちゃの香りが良くて癒されます!」という声ですね。特に香りがいいというお声は多いです。ヒノキってすごく香るので、工房の中などは匂いが充満していて、私たちはもう鼻が慣れてしまってあまり感じないのですが、外から来られたお客様などはやはり、入ってきてすぐに「ああ、いい香り」とおっしゃられますね。
(インタビュアー) 実際に木のおもちゃを作る際にはどんなことに気を付けていますか?
(陽子さん)やっぱり安全性ですね。誤飲チェッカーというものを使ったり、安全面の基準にはかなり気を使っています。ただ、そういった対策をしていても100%安全という訳にはなりません。遊んでいる中で傷がついて破片が出てきたり、もしものことを考えなければいけません。なのでやはり一番大事なのは、大人の方が必ず近くで見守っていただくということだと思いますね。生活の中でそういう恐れのあるものはどこにでも、いくらでもあります。また、見守っていただくことで一緒に過ごす時間やコミュニケーションを大事にすることもできるので、遊ぶときはぜひ子供たちを近くで見守ってほしいです。

▲細部への配慮と親子のコミュニケーション時間を考えた、
安心して楽しめる工夫が詰まっています。
(インタビュアー)遊ぶときは一緒に、という言葉の大切さが分かりますね。
ちなみに、現場には女性の方が多いと聞いているのですが…
(陽子さん)はい。ほぼ女性です。
(インタビュアー)木工などの現場には男性が多いイメージですが、 なぜ女性の職人さんが中心となっていったのでしょうか?
(陽子さん)家具などを作るのと違い、おもちゃを作る作業って作っているものが小さくて結構細かな作業をするので、女性には割と向いていると思うんですよね。なので女性の方が多いです。
和徳さん:あと、都会もそうかもしれませんが、田舎は女性が働く環境として、当時フレックスタイム制を採用している会社ってほとんどありませんでした。そこで、当社ではそれを導入したんです。結果、働きたいけど子育てなどで中々働けないという優秀な女性人材の掘り起こしができました。うちは製造業なのである程度、サービス業と違ってその辺の融通が効くので、そういった自由な働き方が可能でした。
もちろん今でも基本的には一定の期間の中で働く時間は自分で自由に采配することができます。子供の病気や学校行事などの参加の際は全て休めるようにしているので、みんなが連携しながら子育てを応援する形ができています。
(陽子さん)みなさんが何に重点を置いて仕事をしたいかということは全員違うので、その人その人に合わせて都度対応しています。
(インタビュアー)HarForも「自由な働き方」についてすごく大切にしているので、とても参考になります。
(和徳さん)会社の仲間たちも仕事を楽しんで毎日来てくれているなと感じているので、それはやっぱり嬉しいですね。楽しくやれるかどうかが1番大切です。
(インタビュアー)そのために高知の企業に必要なことってなんでしょうか?
(和徳さん)高知は18歳以上の人口が就職・進学などで多く県外に出ていく中で、「人材の獲得」がやはり難しくなっていると思います。だからこそ、高知の企業は田舎であっても都会に負けないぐらいの魅力のある企業になっていかないといけません。
SDGs についても関わる話なのですが、「B Corp認証」ってご存知ですか?
(インタビュアー)初めて聞く言葉です。
(和徳さん)「ベネフィット・コーポレーション」の略で、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する国際的な認証制度のことです。アメリカの民間団体が出しており、日本では2025年3月時点で55社と、取得企業がまだ少ないんです。 中四国ではまだ0なので、うちが今1番のりを狙って取得のために動きを進めています。取得するのがすごく難しいんですよ。申請や面接はすべて英語なんですが、もう申請書類の提出は完了して、今は審査面談の順番待ちをしている状態です。早ければ今年の8月に結果が出ます。
(インタビュアー)それは楽しみですね!
(和徳さん)山のくじら舎は、そういった認証企業の一つである某有名アウトドアブランドを目指して色んな取り組みを行っています。環境保全など、ステークホルダーに対しても世界的に高水準な企業なのですが、弊社もここ高知でそんな地域を引っ張っていける会社を目指し、地域貢献や人材獲得をきちっとしていって、企業として成長させていきたいです。


▲高知県産の木材を活かした製品づくりを通じ、環境保全や地域密着型の取り組みが推進されています。
(インタビュアー)地域に根ざした活動を意識されて取り組まれているのは、高知県民として本当に嬉しいですね。他にも何かそういった取り組みをされているんですか?
(和徳さん)拠点である安芸市には「重要伝統的建造物群保存地区」といって、歴史的町並みを保存・活用するために国から選定されている地区があります。「安芸市土居廓中」というところなのですが、そこは昔の武家屋敷などが古民家として残っていて、住民の方々や市町村と協力して建物の保護や修繕が行われています。弊社も1棟古民家を所有し、建物の保護や修繕を行い、シェアオフィスや地域イベントの会場として活用するというプロジェクトに取り組んでいます。
元々自分が古民家好きだったのもありますが、そういった文化的な活動を通して観光産業にも寄与し、地域にお金を回すことで、少しでも職人さんの技術を残すサポートになるのではと考えています。伝統的建造物群保存地区に指定されたのは2012年のことで、歴史としてはまだ浅く、古い建物に交じって現代的な建物も建っていたりするのですが、そういった建造物たちも長い年月をかけてこれから少しずつ整い、美しい町並みとなっていくと思うんです。会社の事業としてきっかけをつくり、「一緒に守っていきませんか?」という提案を続けています。
(インタビュアー)誰かがやり始めないと誰もやらないままになってしまいますもんね。
(和徳さん)そうですね。
他にも、SDGsの観点から見ると、当社の活動は17の目標の中で、例えばこんなところに関わっていると思っています。
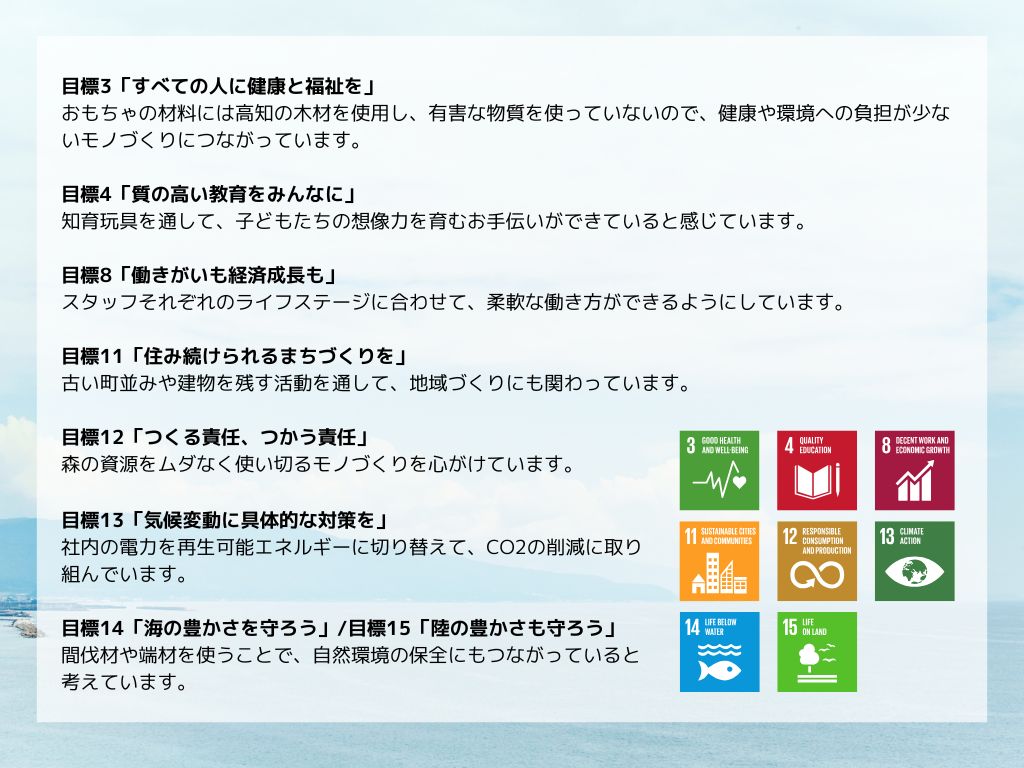
(インタビュアー)製造時に出る廃棄分もとても少ないんですよね。
(和徳さん)はい。非常に少ないです。なので、弊社にはそもそも焼却炉がありません。この地域は食品加工が盛んで筍などを炊く際に薪を結構使うのですが、切れ端などはその薪として提供させていただいています。有害物質がでないので、喜んでいただいていますね。
(インタビュアー)循環型社会の1パーツとして、事業そのものが様々なことと繋がっているんですね。
(和徳さん)このSDGsの先にあるのが、B Corp認証だと思っています。現状認証を取得している企業はほとんどが東京の企業ですが、弊社がB Corp認証を取得できれば、恐らく中四国でも取得したいという企業が出てくると思うので、ぜひ地方でも広まってほしいですね。
(インタビュアー)高知には自然資源に直接関わるお仕事がたくさんありますもんね。
では、こうやって事業展開をされていく中で大変だったことはなんでしょうか?
(和徳さん)もちろん今までたくさんありましたが、それを乗り越えることを楽しんでいましたね。そうすることで自分自身も会社も成長させてもらってきたと感じています。スタッフのみんなも一緒に成長できれば、それがベストです。どこもそうだと思いますが、会社って成長するための場所ですから、日々勉強ですね。
ただ、コロナの影響で少し世の中全体が変わったことの影響は結構大変でした。特に売り方が変わって。以前取引があった百貨店で、売り場の見直しでお取扱いが無くなったり、色んな小売店の営業がストップしたりして、ネットに注力した売り方に舵を切りました。ピンチの時こそむしろアイデアが出るので、結果的に仕事自体にはそこまで大きな問題はなかったのですが、最初はやはり切り替えるのが大変でしたね。


▲困難を楽しみ、乗り越える過程を新たな挑戦に変える前向きな姿勢に感銘を受けました。
(インタビュアー)EC サイトを活用する中でどんなメリットを感じていますか?
(和徳さん)例えば売上の半分を大手企業が買ってくれたとすると、コロナのような出来事が起きたときに、取引が減少してしまう可能性があり、実は結構リスキーなんです。しかしECサイトを使うと、直接一般消費者と取引する形になるので、取引先が幅広く分散されて仕事自体が安定します。そこが私たちにとって1番のメリットですね。
うちではECにかなり力を入れていて、県内ではトップクラスの強さだと自負しています。東京の広告会社に運用してもらい、週1でMTGをして徹底的に運用管理していますね。
(インタビュアー)EC には以前から注目されていたんですか?
(和徳さん)元々10年ぐらい前に本格的に一新していこうと動き始めていました。前回ゲストの毛利製麺株式会社の毛利さんも通っていた、ECを活用した商売のための塾があって、そこに入って色々と教えてもらいました。
(インタビュアー)これからも、どんどん事業拡大・成長していくと思いますが、目標はありますか ?
(和徳さん)先ほどお話した「B Corp認証」というのは、会社を成熟させていくためにあるんですよね。なので、会社を成熟させていって、田舎でも多少なりともやっていけるということを証明し、同じように田舎で頑張っていこうとしている企業のお手本になっていきたいと思っています。
その上で参考にしているのが、私たちが目標としている某有名アウトドアブランドが掲げている「負担を負う権利」という言葉です。元々はカナダのインディアンの言葉らしいのですが、先頭に立つリーダーポジションの人たちが、義務ではなく権利として負担を率先して負っていくことが大事なんじゃないかと言っている言葉です。「負担」というものを、しんどくてめんどくさい「義務」ではなくて、負うことができる「権利」なんだと知れば、色んなことがすごく面白くなると思うんです。僕も初めて聞いた時に心が痺れました。環境保全や文化保護などの活動も、「義務」じゃなくて「権利」です。
(インタビュアー)なんだかさらに人生を楽しめそうな言葉ですね。
(和徳さん)僕今すっごく楽しいですもん(笑)
それともう1つ、この安芸市を高知の「玩具産地」にしたいなとも思っています。自分の生きてる間に実現するのは無理かもしれませんが、そのきっかけとなる1番最初の種になりたいですね。B Corpの活動を通して会社を成熟させ、「生活と仕事が一体になるような暮らし」の提案ができればいいなと思いますし、その姿を見て同じような会社を目指す企業が生まれるきっかけになれば嬉しいです。

▲女性職人さんたちがひとつひとつ手作業で作られているそう。
(インタビュアー)それはぜひ実現してほしいですね。
奥様はお仕事を続けていく中で、今後の目標などはありますか ?
(陽子さん)目標ではないかもしれませんが、自分が好きなことを仕事にでき、ずっと続けてこられたのは本当にありがたいことだといつも思うので、これが今後も変わらず続けられたらいいなと思います。息子はもう成人して県外で働いてるので、今は自由な時間がたっぷりあります。普段の仕事では機械も使ったりするのですが、仕事以外の趣味として、「グリーンウッドワーク」という、電動の機械を全く使わずに手作業で木を削ってものを作るということをやっているんです。その趣味を、仲間たちと休日に楽しめたらと思っています。
なんだか結局、休みの日も木を削ってますね(笑)
(インタビュアー)本当に物作りがお好きなんですね〜!素敵です!


▲グリーンウッドワークの様子
(和徳さん)私たちも 50歳を超え、あとはどうやって遊んで生きていこうかなと考えていて(笑)人生は絶対に楽しんだ方がいいですよ。働きすぎないように遊ばないとだめです!
インタビュアー:これまでのゲストのみなさんも、 人生を全力で楽しもうとしているからこそ、キラキラしてるんだなといつもすごく感じています。本当にやりたいことがまだまだいっぱいあって行動されている姿は、読者のみなさんもすごくエネルギーと勇気がもらえていると思います。
和徳さん:行動するのはやっぱり大事です!工房のお手洗いに20年以上貼ってるガンジーの言葉があるんですが、私もそれを毎日見て奮起しています。
“小さな改革もできないものが大きな改革を達成できるわけは決してありません”
みなさんもぜひ日々、小さなことからでいいのでチャレンジしてほしいですね。
今回の取材内容以外にも、色んなお話をお聞きできました。そちらの楽しい取材の様子も、番外編としてHarForの公式Xで順次公開しますので、ぜひチェックしてみてくださいね!
お二人とも、取材へのご協力本当にありがとうございました!
次回、萩野さんご夫婦はどんなゲストにバトンを渡してくれるのでしょうか。お楽しみに!
◆HarForが取り組む女性活躍推進の関連記事はこちらから
◆時短勤務等多様な働き方を支援するHarForの採用サイトはこちらから
◆前回の記事はこちらから
◆次回の記事はこちらから
(インタビュー・写真:HarFor広報担当)